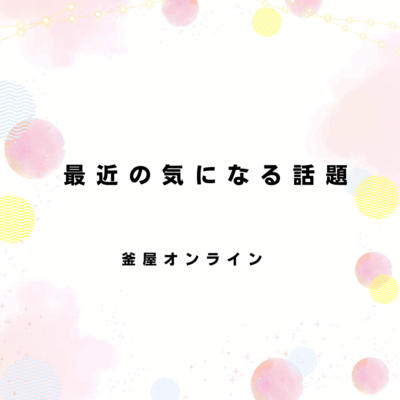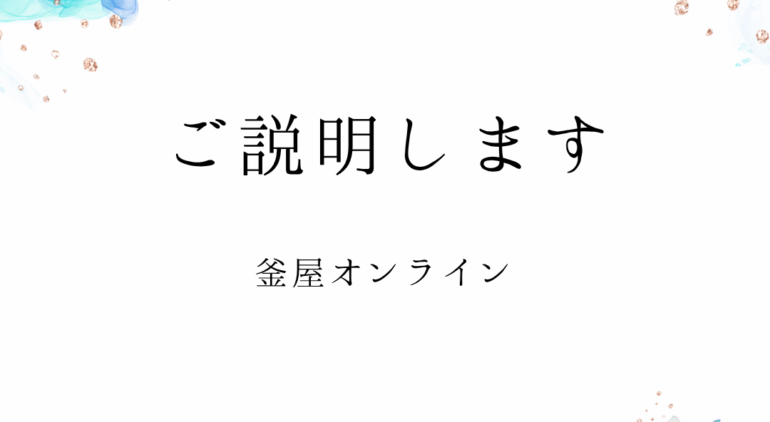
機密保持契約を結ぶとはどういうことか? 釜屋オンライン
🏢 機密保持契約(NDA)とは
目的:
商談・協業・試作・開発・見積りなどの過程で知り得た相手方の機密情報を、
第三者に漏らさず、自社でも不正に使わないように定めた契約。
つまり、「相手の秘密を守ります」という約束を法的に明確化するものです。
主に、取引前(検討段階)や技術打ち合わせの前に締結されます。
📜 NDAで定める主な内容(構成の概略)
以下のような項目が盛り込まれます:
| 項目 | 内容の概要 |
|---|---|
| 1. 機密情報の定義 | 契約で保護される情報の範囲を明確化。技術情報(図面・仕様書・試験データなど)、営業情報(価格表・顧客リスト・契約条件など)、経営情報(計画・戦略)などが対象。 ※口頭情報も「後日書面化」されれば対象になるケースあり。 |
| 2. 機密情報の除外事項 | すでに公知の情報、入手前から知っていた情報、第三者から正当に入手した情報、独自に開発した情報は「機密情報ではない」と定める条項。 |
| 3. 利用目的の限定 | 相手から得た情報を「契約目的以外に使ってはならない」。例:「A社からの見積依頼のためだけに使用可」。自社製品開発などに流用すると違反。 |
| 4. 第三者への開示制限 | 相手の許可なく第三者(自社の他部署・協力会社含む)へ提供してはならない。例外的に必要な場合は「同等の秘密保持義務を課すこと」。 |
| 5. 複製・コピーの制限 | 資料やデータのコピー、持ち出しを制限。試作データや図面も含まれる。 |
| 6. 保管・管理義務 | 情報を適切に保管し、紛失・漏洩を防ぐ措置を取る義務。紙・電子データ両方対象。 |
| 7. 契約期間/有効期間 | 通常「契約締結から○年間」「情報開示から○年間」など。 多くは2〜5年。ただし守秘義務自体は契約終了後も継続。 |
| 8. 契約終了時の取扱い | 受領した情報は返却・破棄する義務を明記。 |
| 9. 損害賠償 | 秘密漏洩や目的外使用が発覚した場合の責任・賠償条項。 |
| 10. 準拠法・合意管轄 | 紛争が生じた際にどの法律・裁判所に従うかを定める。日本国内取引では「東京地裁」などを指定することが多い。 |
🔐 NDAが「制約する」こと(義務・禁止の範囲)
機密保持契約は、主に以下の行為を制約・禁止します。
- 相手から受け取った情報を 他社・外部に漏らすことの禁止
- 得た情報を 目的以外に使用することの禁止(=自社の開発・営業に使えない)
- 書類・データを 複製・転載・社内共有することの制限
- 契約終了後に情報を保持・利用することの禁止
- 管理を怠って 漏洩を招いた場合の責任
つまり、情報を「知ってしまった後」にどう扱うかを縛る契約です。
違反すれば、損害賠償請求・取引停止・信用失墜のリスクが発生します。
⚙️ 実務上の注意点(中小企業が特に気を付けるべきこと)
- 「一方的な内容」になっていないか確認
→ 相手(大手)が情報開示者となる片務契約型の場合、こちらの情報が保護されないことも。
→ 双方の情報を守る「相互NDA」形式が望ましい。 - 情報の範囲を広げすぎない
→ 「契約書に関するすべての情報」と広範に書かれていると、日常的なやりとりまで制約対象になる。
→ 「開示時に明示したものに限る」など範囲を明確にしておく。 - 実際の運用ルールを社内で共有する
→ 営業担当・技術担当などが「NDAを結んだ案件」かどうかを把握していないと、メール添付や資料転送で違反の恐れ。
→ 「NDA案件リスト」「資料管理フロー」など簡易ルールを整備。 - 電子データも同じ扱いに
→ 図面・3Dデータ・画像なども対象。クラウド共有やUSB持出しにも注意。 - 契約終了時の返却・削除を実行する
→ 「破棄した」証跡(削除報告書・返却記録)を残すことが望ましい。
💡 NDAは“信頼を示す契約”
- NDAは「疑っている」契約ではなく、「安心して情報を交換するための信頼の証」です。
- 特に技術系・製造系の取引では、NDAを交わしていない企業は「情報管理意識が低い」と見られることもあります。
- 大手企業は、サプライヤー・委託先の選定条件として「機密保持体制」を重視しています。
中小企業にとっても、
「守る仕組みを持つ会社」は取引先から信頼される会社です。
⚠️ 1. 見落としがちな「情報漏洩のパターン」
NDAを結んでも、次のような“うっかり漏洩”が後を絶ちません。
どれも悪意ではなく、管理の甘さや認識のズレから起きています。
| パターン | 内容・原因 | よくある実例 |
|---|---|---|
| ① メール・添付資料経由 | 他案件の資料を間違えて添付/宛先のCC・BCC誤り | 「A社向け提案書」を「B社」に誤送信。類似案件で内容が似ていた。 |
| ② 協力会社への再委託 | 相手の承諾なしに、協力業者へ図面を回す | 下請に見積依頼をかけたが、NDAの範囲外だった。原図をコピーして送付。 |
| ③ 社内での安易な共有 | 別部署のメンバーが資料を見られる状態に | 営業フォルダに顧客別資料を共有設定、誰でも閲覧可能になっていた。 |
| ④ 打ち合わせ・展示会などの口頭漏洩 | 雑談や名刺交換時に技術情報を口頭で話す | 展示会で同業者に「この技術を共同開発している」と話してしまった。 |
| ⑤ 退職・異動時のデータ持ち出し | USB・個人PC・メール転送などによる意図せぬ持出し | 退職前に自分の仕事履歴を保存したつもりが、NDA対象データを含んでいた。 |
| ⑥ 廃棄・返却ミス | 契約終了後の資料や試作品を破棄せず保管 | 数年後、別案件で再利用してしまい、相手から指摘を受ける。 |
| ⑦ クラウド・外部ストレージの設定ミス | 共有URLを「全員アクセス可」に設定 | DropboxやGoogle Driveの共有リンクを社外でも開ける状態に。 |
🔸共通点:
「契約を守る意思はあるのに、運用ルールが不十分」なケースが多い。
つまり、“仕組み漏洩”が最も多いのです。
⚙️ 2. よくあるトラブル・実際の影響
▶ ケース①:試作見積段階での情報再利用
ある中小部品メーカーが、大手企業から試作品見積を受け、図面を預かりました。
見積後に他社の新規案件で似た設計があったため、
「参考にしただけ」として類似設計を流用。
数ヶ月後、大手企業が展示会でそれを発見。
→ 「守秘義務違反」に該当し、**取引停止・損害賠償請求(数百万円規模)**に発展。
→ 社長は「図面を流用したつもりはなかった」と主張したが、
“外観が酷似”していたことが決定的だった。
教訓: NDAでは「目的外使用」が最大の落とし穴。
「参考にしただけ」も違反になる可能性があります。
▶ ケース②:下請け企業への情報提供トラブル
製造委託の下請企業に対して、元請が顧客から預かった設計図面をそのまま転送。
下請け側では、社内共有フォルダに保存しただけだったが、
別の営業社員が誤ってその図面を他の見積案件に使用。
→ 元請・下請ともに責任を問われ、二社で共同賠償。
→ 双方の信頼関係も崩壊。以後の取引は白紙に。
教訓: 「NDAを結んだのは誰か」を曖昧にしない。
再委託先に再開示する場合は、別途NDAの締結が必須です。
▶ ケース③:退職者の持ち出し事故
設計担当者が退職時、自分の実績ポートフォリオとして
過去の設計データや図面をUSBにコピー。
後に転職先企業がそのデータを参考に製品設計を行い、元の取引先から発覚。
→ 元社員・転職先企業・元勤務先の3者に影響。
→ 結果的に、元勤務先(守秘義務を管理できなかった側)も責任を問われた。
教訓: NDA違反は「個人の過失」でも会社責任に及ぶ。
退職・異動時のデータ管理ルールを明文化すべき。
💣 3. NDA違反の“責任の重さ”を感じるエピソード
「悪意がなくても、漏れた瞬間に『契約違反』になる」
というのがNDAの怖さです。
ある製造業社長の体験談です。
「数年前、ある大手の開発案件でNDAを結び、
試作のために受け取った技術資料を社内サーバに保管していました。
その後、別の取引先が同じ分野の開発を依頼してきたとき、
社員が“似た資料がある”と誤ってそれを参考にしてしまったんです。
結果的に、当社の社内監査で発覚。相手企業にも報告しました。相手からは“意図的でない”と理解してもらえましたが、
取引は中止となり、信頼回復に2年以上かかりました。
損害賠償よりも、“信頼を失った痛み”の方が大きかった。」
→ 結論: NDAの本質は「契約書」ではなく「信用契約」。
守るかどうかが、次の取引を得るか、失うかを左右します。
🧭 まとめ:NDAは“信頼の証”であり“経営リスクの防波堤”
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 秘密情報を安全に共有し、安心して協業できる関係を作るため |
| 脅威 | 人的ミス・再委託・退職・口頭情報などから漏洩が起こる |
| 結果 | 損害賠償・取引停止・信用失墜など経営への直撃リスク |
| 対策 | NDA締結+社内教育+情報管理ルール+責任意識の共有 |
釜屋オンライン