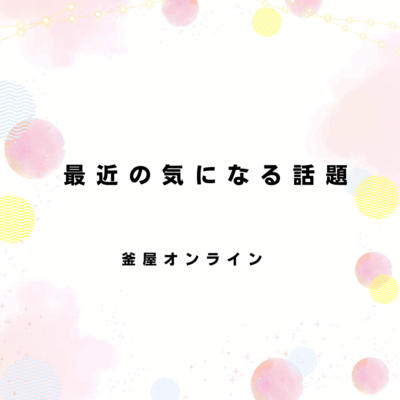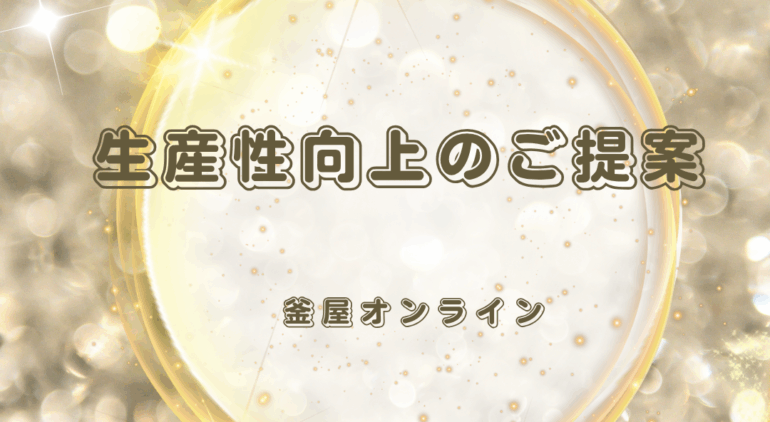
AIが変える金型・成形現場 ― 不良を“予測する”モノづくりへ
AIの導入は工作機械だけでなく、金型や射出成形の現場にも広がっています。不良品を予測し、金型寿命を見極め、成形条件を自動調整する――AIが“経験と勘”を可視化する時代です。今回は、管理職として押さえておくべき導入ポイント・現場運用の課題・実例をQ&A形式で整理します。
金型や射出成形の現場では、これまで職人の“勘”と“経験”に頼ってきた加工条件設定・金型交換・不良発生対応などが、AI+センサー+データ分析によって変化し始めています。例えば、成形機の金型内圧力データをAIに学習させ、異常を検知・条件をリアルタイムに最適化するシステムなどが商品化されています。
こうしたシステムは「経験者不在の現場」「多品種変量生産」「夜間無人運転」などの課題を抱える製造現場において、品質安定と稼働率向上の大きな武器となります。
・現場センサーとデータ収集体制の構築:金型内圧・温度・流動バランスなど、入力データを揃えることが成功の鍵。
・AIモデル構築:学習用データの蓄積、異常パターンの定義、フィードバックループの設計。
・運用体制:システムが出した“アラート”や“最適化条件”を現場がどう受けて動くか、役割・判断ルールをあらかじめ整理しておく。
・弊害への対応:AI導入が目的化し、現場に“監視システムを入れるだけ”となってしまうと、技術者のモチベーションが下がる場合もあります。管理職として「AIが何を変えるか」を明確に伝え、現場の巻き込みを図ることが重要です。
Q&A形式で整理
Q1. AIを入れたら“誰も手を動かさなくていい”ということ?
A1. いいえ。AIは“最適化された条件”“不良発生の予兆”を提示しますが、最終判断・現場判断・保守運用はいまだ人が担います。AIと現場技術者が協調する仕組みを作ることが成功の鍵です。
Q2. 導入コストがかかるが、投資回収の目安は?
A2. 品質不良率低減、段取り時間短縮、金型寿命延長、夜間稼働の確保などの数値化ができれば、2~3年で回収可能という事例もあります。例えば、成形不良率を5%→2%に下げたことで、スクラップ・手直しコストが月額数百万円単位で改善された例があります。
Q3. 技術に慣れていない現場でも導入できるか?
A3. はい。ただし“段階的導入”が現実的です。例えば、まず金型内圧だけを監視→異常時アラート→条件変更という流れから始め、次に複数パラメータを統合して最適化へというステップがおすすめです。
AIを金型・成形現場に導入することで、「経験者がいない」「変数が多い」「夜間運転が難しい」といった製造現場の悩みをデータと技術で解決できます。ですが、技術そのものが目的化してはいけません。導入目的を現場課題に結びつけ、運用まで踏み込んだ体制構築が重要です。設備・システム導入をご検討の際には、ぜひ私ども 釜屋株式会社 機械部にご相談ください。御社の課題を共有し、よりよい製造現場へのお手伝いをいたします
釜屋オンライン