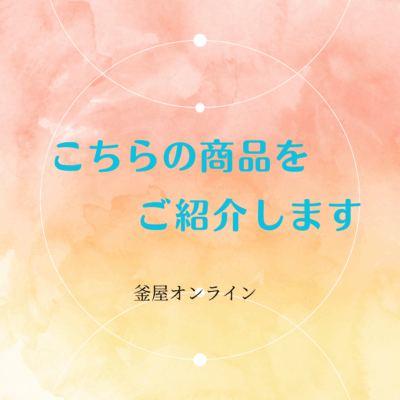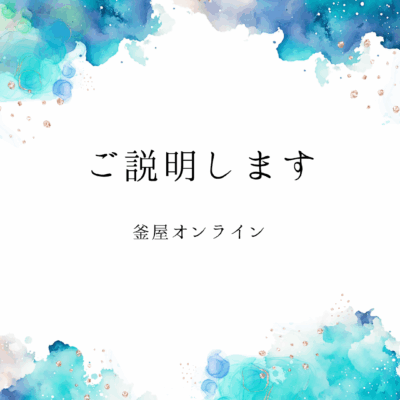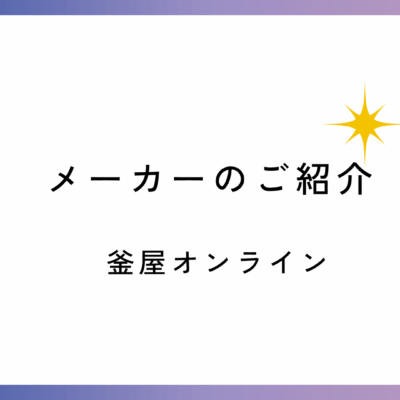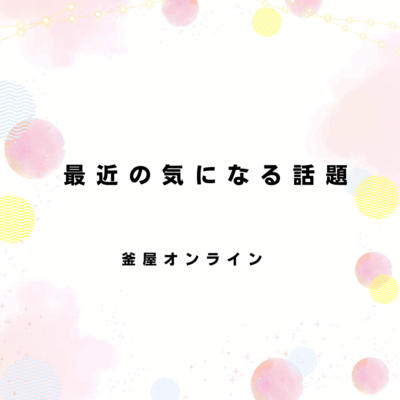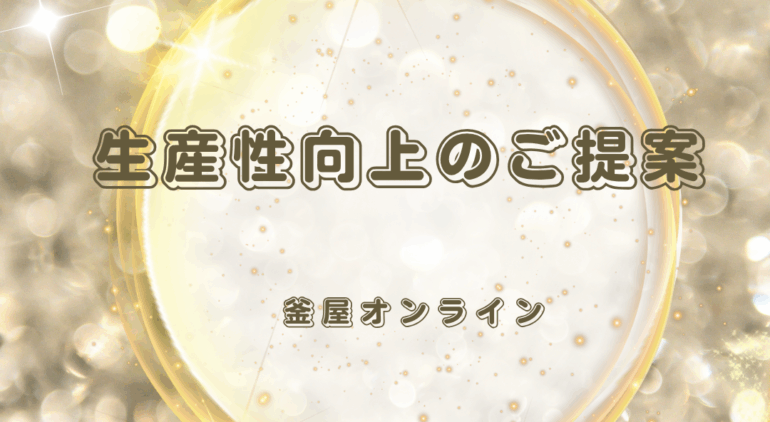
3Dプリント×切削 ― ハイブリッド加工が変える金属加工の未来
金属3Dプリンタと切削加工が融合する「ハイブリッド加工」。一品物から金型補修、軽量部品まで、従来の製造常識を覆す可能性を秘めています。今回は、技術トレンド、導入のポイント、実例をQ&A形式で整理し、押さえておくべき戦略をお伝えします。
近年、金属積層造形(AM)と切削加工を1台のマシン・1プロセスで行えるハイブリッド機が登場しています。
たとえば、スペインMeltio社の「Meltio Engine CNC」はマシニングセンタの主軸に積層ヘッドを組み込み、造形+切削が可能な装置です。また、金属3Dプリンタ造形+切削による追加工を“ハイブリッド造形”と称し、時間・コストを削減した事例も紹介されています。
こうした技術は、金型補修、軽量構造部品、試作・小ロット量産で特に効果を発揮します。
<導入ポイント>
・用途選定:まずは金型補修・深リブ形状・内外配管構造など“切削だけでは難しい形状”から検討。
・設備運用:ハイブリッド機は造形+切削両方を含むため、材料管理(金属ワイヤー・粉末)、造形条件、切削条件、後処理まで運用を見据えること。
・コスト設計:AM材料や装置費は依然高めですが、工程統合によるリードタイム短縮・材料削減・在庫削減がメリット。ROI設計を早期に行うことが重要です。
・技術育成:造形条件・切削条件・融合加工のノウハウが必要です。「これまで切削だけ」だった加工現場に、AMをどう組み込むかアイデアが重要です
Q&A形式で整理
Q1. ハイブリッド加工は量産にも使える?
A1. 現状、量産向けというよりは試作・補修・少量多品種向けですが、軽量構造部品・航空宇宙部品では量産適用が進みつつあります。例えば、金属3Dプリンタによる造形+切削仕上げで軽量化を達成した部材があります。
Q2. 導入リスクは何?
A2. 主なリスクは材料コスト・造形品質(密度・残留応力)・後処理時間・技術習熟の手間です。また、造形と切削の“境目”で品質が出ないと、コストメリットが出ません。まず“限定用途でのパイロット導入”から始めるのが得策です。
Q3. 切削のみの加工を辞めて全部ハイブリッドにすべきか?
A3. いいえ。切削には依然コスト・速度・工具寿命の面で優れた点があります。ハイブリッドは“切削が難しい/段取り工数が大きい”部品で効く手法です。管理職としては“適材適所”でハイブリッドを検討すべきです。
ある金型製作企業では、摩耗・破損した金型補修にハイブリッド機(造形+切削)を導入。旧方式では補修に10日を要していたが、ハイブリッド導入後は5日で完了、コストも30%削減。さらに、補修後の金型寿命が20%延び、夜間稼働への移行も可能となりました。これは“切削では難しいリブ構造+補修部積層”という用途に対応した事例です
ハイブリッド加工は、製造業のありかたを変える可能性を秘めています。
“どの部品/用途に適用可能か”を検討し、まずは限定的な用途から導入してみて経験値を積むことがポイントとなります。
もし、ハイブリッド加工機やその運用にご興味を持たれましたら、ぜひ私ども 釜屋株式会社 機械部にご相談ください。
釜屋オンライン