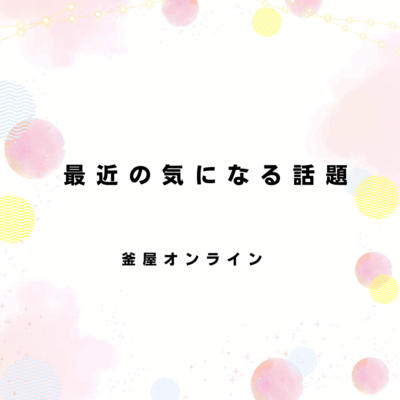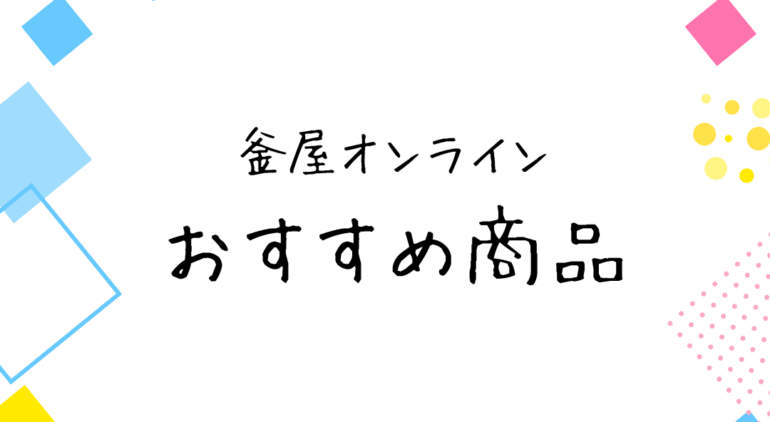
CADからCAMへ ― 加工プログラムの自動生成がもたらす変革
熟練プログラマーの不足、段取り時間の増加――これらの課題に対する切り札が「CAD/CAM連携」です。設計データと加工データを一貫させ、自動化・標準化を図ることで、製造リードタイム短縮と技術継承が進みます。今回は押さえるべき導入ポイント、実務活用のQ&Aと事例をご紹介します。
CADで設計された3DデータをそのままCAMへ流し、工具パス生成・干渉チェック・段取り条件まで自動設定できる環境が浸透しつつあります。たとえば、国内金型メーカーが早期に3次元CAD/CAMを導入し、「加工プログラム作成が当たり前」になっている事例があります。
このような連携によって、プログラミング時間が大幅に短縮され、精度・再現性・技術継承にも寄与します。
<導入ポイント>
・目的整理:短納期・多品種・複雑形状への対応という製造課題を明確に。
・データ整備:設計データ(CAD)がCAMにスムーズに渡るためのデータ準備・設計ルール統一。
・ソフト選定・運用体制:定期的なバージョンアップ、現場技術者の教育、加工ノウハウのテンプレ化。
・KPI設定:プログラム作成時間削減率、加工ミス削減、設備稼働改善などを数値化。
Q&A形式で整理
Q1. CADだけ、CAMだけでもダメ?
A1. それぞれ単体でも有効ですが、連携することで「設計⇒加工」までの流れがスムーズになり、段取り削減・ミス減・技術継承が可能となります。
Q2. 初期投資が大きく見えるが、費用対効果は?
A2. 導入先の事例では、プログラム作成時間を30~50%削減、試削回数減少による材料/電力コスト削減、工程リードタイム短縮などが出ています。特に若手技術者の育成・ノウハウ共有という無形価値も大きいです。
Q3. データ断絶・旧設備との兼用はどうすれば?
A3. 段階的な導入が現実的です。まずは設計部門からCAD標準化、次にCAMのテンプレート化、最後に加工現場との連携。既存設備でもデータ活用できるように“中継データ”や“変換ルール”を設けることがポイントです。
CADからCAMへ、設計と加工をつなぐデータフローの実現は、製造現場の“当たり前”を変える鍵です。
若手育成、段取り時間削減、多品種対応…管理職としては“技術継承”という観点も併せて考えてみてはいかがでしょうか?
もし、CAD/CAM導入・運用を検討される際には、ぜひ私ども 釜屋株式会社 機械部にご相談ください。
御社に最適なソリューションをご支援いたします。
釜屋オンライン